Booost株式会社
実践型でサステナビリティ経営を「競争力の源泉」「企業価値向上」へ結びつけるCEO・CFO等の経営層および、経営企画・財務・サステナビリティ実務担当者向けのプログラムを実施
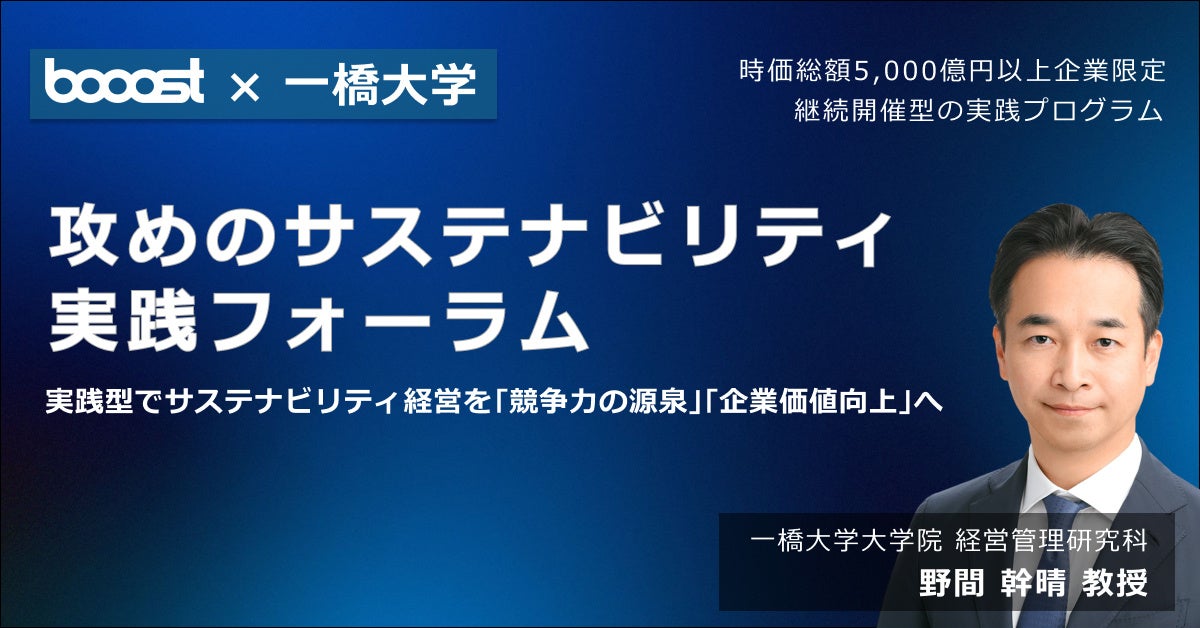
大手企業でシェアNo.1*を誇る「サステナビリティERP*1」の提供と、「サステナビリティ2026問題*2」の提唱を通じて企業のSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)*3を支援するBooost株式会社(東京都品川区、代表取締役:青井宏憲、以下 当社)は、一橋大学大学院 野間幹晴 教授と連携し、「攻めのサステナビリティ 実践フォーラム」を開設いたします。
本フォーラムは、時価総額5,000億円以上の上場企業のCEO・CFO等の経営者、ならびに経営企画・財務・サステナビリティ部門の実務担当者を対象とし、2026年1月に初回プログラムを開催予定です。
■ フォーラム開設の背景 ―Values(価値観)とValue(企業価値)をつなぐ
これまでのサステナビリティ施策は、企業理念やCSR(企業の社会的責任)といった「Values(価値観)」を軸に語られることが多く、経営戦略や財務成果との直接的な連動は限定的でした。しかし近年、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が定めるグローバル基準など国際的な開示基準の整備、国内でのサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の本格化、投資家・規制当局による企業価値創出への期待の高まりを背景に、サステナビリティを経営戦略の中核に据え、持続可能な企業価値「Value」に直結させる動きが急速に進んでいます。
こうした社会的潮流を踏まえ、当社は一橋大学と共同で、経営層が自らの戦略を再定義し、定量的な財務インパクトを伴って実行に移すための実践的なフォーラムを立ち上げます。
■ フォーラム概要
名 称: 攻めのサステナビリティ 実践フォーラム
開設日: 2026年1月 (予定)
代 表: 一橋大学大学院 経営管理研究科教授(経営管理専攻) 野間 幹晴 教授
対 象: 時価総額5,000億円以上の企業のCEO・CFO等の経営層
および経営企画、財務、サステナビリティ部門の実務担当者
形 式: 対面開催
経営層向けプログラム 年2回 / 実務担当者向けプログラム 月1回
会 場: 如水会館(東京都千代田区一ツ橋2丁目1−1)
参加メリット:
経営層
・ マクロ視点からのサステナビリティ開示、ファイナンスについて理解を深められる
・ 先進企業の第一人者と近い距離でハイレベルな対話機会が得られる
実務担当者
・ 他社との意見交換を通じて実務に役立つ知見を得られる
・ 財務マテリアリティ分析を通じて社内巻き込みの視点を養える
・ 最新テクノロジーの活用可能性を理解し実務応用を検討できる
・ スポンサー役員への報告機会により社内への影響力を高められる
お問い合わせ:
Booost株式会社 「日本をSX先進国へ」プロジェクト事務局
e-mail: 2026SX@booost-tech.com (担当:瀧澤、榎本)
■ 一橋大学大学院 野間 幹晴 教授 コメントおよびプロフィール

<コメント>
サステナビリティは企業理念の象徴であるValuesにとどまらず、いかにValue(企業価値)へと結びつけるかが問われる時代に入りました。本フォーラムでは、理論と実務を往復しながら、経営層が主導する形でサステナビリティを戦略実装へ落とし込むための議論と実践を進めてまいります。本フォーラムに参加された皆様と企業価値向上に向けて議論し、各社の企業価値が向上することを楽しみにしています。
<プロフィール>
一橋大学大学院 経営管理研究科(HUB)教授(経営管理専攻)、同役員補佐(社会連携)
野間 幹晴(のま みきはる)氏
一橋大学商学部卒業、同大学大学院商学研究科修士課程修了。同大学院で博士後期課程修了(博士(商学)取得)。 2002年横浜市立大学商学部専任講師、2003年同大学助教授。 2004年10月、一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授、2007年4月から同准教授、2018年4月から一橋大学大学院経営管理研究科教授、2019年4月より同教授。専門は財務会計・企業価値評価であり、企業価値・財務行動に関する深い研究実績を有し、政策提言や実務連携に積極的で、外部取締役や政策委員会等の役割を通じて、産学連携を強く推進。
著作『退職給付に係る負債と企業行動-内部負債の実証分析』(2020年, 中央経済社)により,2020年度・第63回日経・経済図書文化賞、2021年日本会計研究学会太田・黒澤賞、2021年度国際会計研究学会学会賞、2022年日本経済会計学会学会賞を受賞、『業績予想の実証分析企業行動とアナリストを中心に』(奈良沙織との共著,2024年,中央経済社)により,2024年日本公認会計士協会学術賞を受賞、『二項動態経営 共通善に向かう集合知創造』(野中郁次郎・川田弓子との共著,2024年,日経BP 日本経済出版)。
■ サステナビリティ2026問題の解決を目指す「日本をSX先進国へ」プロジェクト

現在、多くの企業がサステナビリティ関連財務情報の開示義務化にあたって、着手遅れや、それに対する危機感の不足から、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念のある状態である「サステナビリティ2026問題」に直面しています。この問題を乗り越え、日本企業のSX推進や企業価値向上を通じたグローバルでのプレゼンス向上を目指すため、当社は、2024年11月に「日本をSX先進国へ」プロジェクトを立ち上げました。
本プロジェクトでは、現場の実務担当者と経営層(エグゼクティブ)それぞれに向けたイベントや支援施策を並行して展開しています。今回のフォーラムも、プロジェクトの一環として開設しました。
「日本をSX先進国へ」プロジェクトサイト(賛同企業募集中)
■ Booost株式会社について
当社は、国際開示基準に準拠し、環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ関連財務情報の収集、集計の自動化、およびリアルタイムでのモニタリングを可能とする統合型SXプラットフォーム、サステナビリティERP*1「booost Sustainability」の開発提供を行っています。「booost Sustainability」は、グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループやサプライチェーンを含む組織において、多階層の承認フローを実装可能であり、また第三者保証等にも対応できるよう設計されたプラットフォームです。
サステナビリティ関連財務情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。提供開始以降、大企業を中心に、85ヶ国以上、約2,000社192,000拠点以上(2025年2月時点)に導入され、年商5,000億円以上規模の企業においてベンダー別売上金額シェアNo.1*を獲得しております。また、サステナビリティコンサルティング事業も展開しており、SX領域において、企業のプロジェクト推進に伴走し企業価値向上に貢献しています。
<会社概要>
会社名: Booost株式会社
所在地: 東京都品川区大崎一丁目6 番4 号新大崎勧業ビルディング10階
設 立: 2015年4月15日
代表者: 代表取締役 青井 宏憲
資本金: 18億円(資本準備金含む)/2025年2月時点
事業内容: ・「booost Sustainability」の開発運営
・サステナビリティコンサルティングサービスの提供
コーポレートサイト:https://booost.inc/
booost及びBOOOSTは、Booost株式会社の登録商標です。
*出典:ITR「ITR Market View:予算・経費・サブスクリプション管理市場2025」サステナビリティ情報管理ツール市場(売上規模別)-年商5,000億円以上:ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測)
*1 サステナビリティERP「booost Sustainability」は、自社およびサプライヤーのサステナビリティ関連財務情報を管理する“統合型SXプラットフォーム”です。国際開示基準に準拠した環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ関連情報の収集、集計を自動化し、リアルタイムでのモニタリングを可能にします。グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループやサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、サステナビリティ関連情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。提供開始以降、85ヶ国以上、大企業を中心に約2,000社(192,000拠点以上。2025年2月時点)に導入されています。
*2 「サステナビリティ2026問題」とは
サステナビリティ情報の開示義務化にあたって、多くの企業で着手が遅れており、その危機感も不足しているため、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念がある状況のことです。当社では2026年までにサステナビリティデータを経営へ利活用できる体制を構築することの重要性を提唱しています。
(日本をSX先進国へプロジェクト:https://booost-tech.com/2026sx/)
*3 サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)とは
社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指す。「同期化」とは、社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味している。(出典:伊藤レポート3.0)