ANRI
独立系ベンチャーキャピタルANRI(東京都港区:代表パートナー 佐俣アンリ、以下 ANRI)は、日本の基礎科学研究への支援として、人文系分野で未来を切り拓く意欲的な若手研究者を対象にした給付型奨学金プログラム『ANRI 人文奨学金:未来を考える人文フェローシップ』を実施し、この度、第1期生として、新たな視点から未来を考える/切り拓く問いを生み出す若手研究者学生10名を採択したことをお知らせいたします。
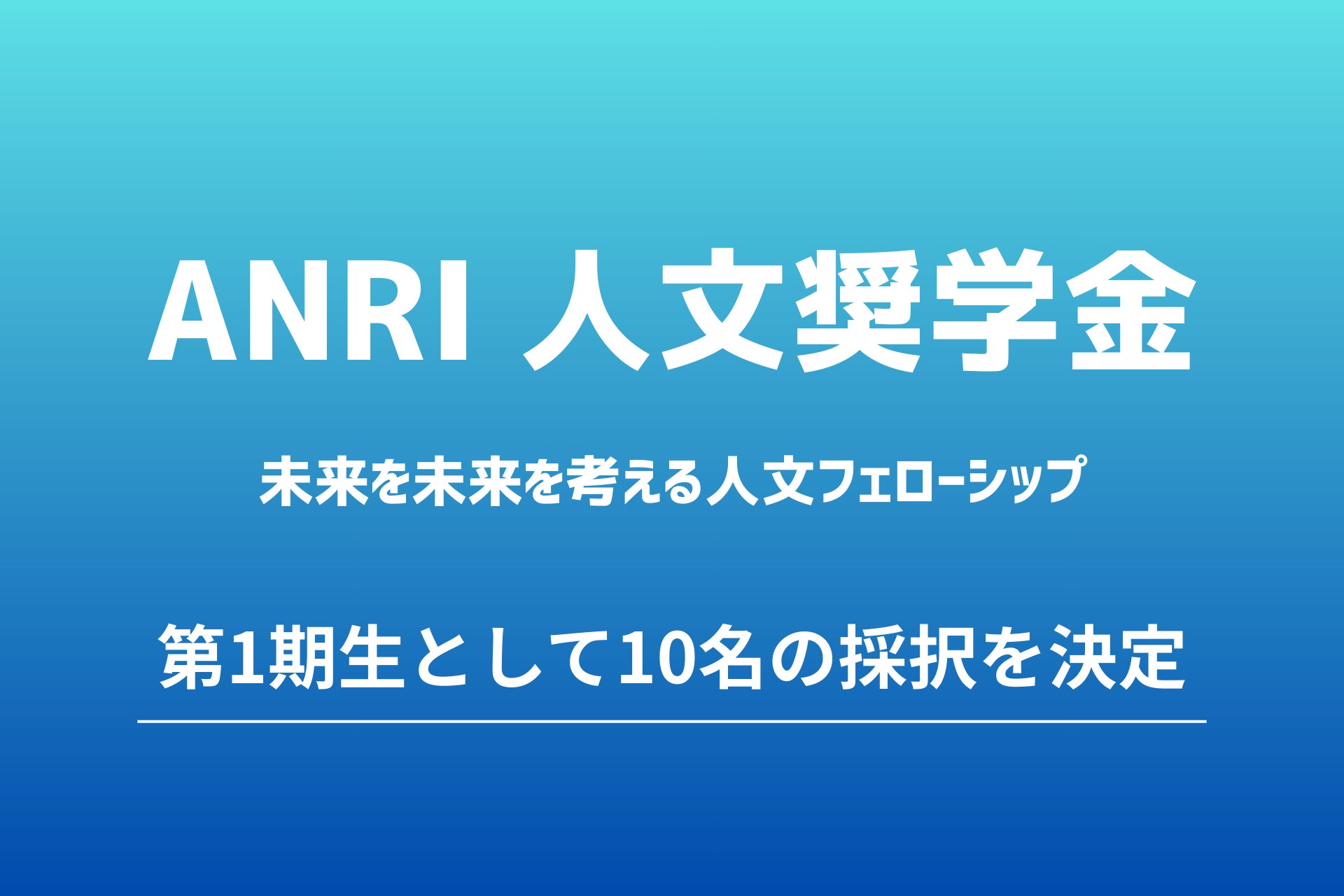
ANRIはこれまで、技術革新や社会変革を目指すスタートアップ企業への投資や、自然科学系の基礎科学研究者の支援を通じて「圧倒的未来」というミッションの実現に取り組んできました。
一方、急速に進化するテクノロジーがもたらす社会的影響を考えるとき、テクノロジーへの理解だけでなく、人間や社会、思想への深い洞察が不可欠であると強く感じるようになりました。
そこで今回、社会をより良い方向へ導く可能性を秘めた人文系研究への支援が不可欠であると判断し、新たに「ANRI 人文奨学金:未来を考える人文フェローシップ」を立ち上げました。
本奨学金を通じて、学際的な交流と新しい視点の創出を促進し、テクノロジーと人文知が掛け合わさる未来を共に考えていきます。
奨学金概要
名称:ANRI 人文奨学金:未来を考える人文フェローシップ
採択人数:最大10名
助成金額:1人あたり50万円(2025年9月下旬に一括支給)
助成期間:採択より1年間
使途:研究活動のためであれば自由(領収書等不要)
一度のみの助成。再申請は不可(落選した場合は次年度以降の応募が可能)
『ANRI 人文学奨学金』第1期生採択者のご紹介
大野 瑞記(南山大学大学院人間文化研究科・博士後期課程1年)
「兵士の経験に目を向けた戦争倫理の再構成」
私の研究は、戦争倫理学という分野において、戦場の直接の行為者である兵士のあり方や倫理的経験から、戦争とそこにある倫理を哲学的に捉えなおす試みです。従来の議論の多くは、国家の判断や制度的正しさ、あるいは戦争の被害者となる民間人に関する問題を中心的に扱ってきました。そこで本研究は、これまであまり目を向けられてこなかった、戦場という特異な極限状況で実際に行為する兵士の生や彼らのあり方に注目することで、より実状に根ざした戦争倫理の理論的再構成を目指します。抽象的で現実の社会とはやや距離があるように思われがちな哲学・倫理学ですが、理論研究と現実の経験や問題とを絶えず往還する生きた思考としての哲学は、現代社会とともにあるものであり得ると私は考えます。この度は、ANRI人文奨学金に採択していただき、心から感謝しております。いただいたご支援を力に、こうした私なりの哲学の実践を通じて学術と社会をつなぐ研究を深めてまいります。
岡本 隣(東京大学大学院総合文化研究科・修士課程2年)
「20世紀前半の日本における性ホルモン研究の展開:無知学・フェミニスト科学論の観点から」
ANRI人文奨学金に採用いただき誠に光栄に存じます。
私の研究は、フェミニズムの蓄積を踏まえ、科学・技術と社会の関係を批判的に検討する「フェミニズム科学論」及び、文化間の知識のギャップに着目する「無知学」に立脚しています。性差にまつわる科学研究がジェンダーバイアスと無縁ではないことは、これまで主に西洋圏における科学研究を事例として明らかにされてきました。ところが、現在に至るまで日本の科学界を対象とする同種の研究はほとんど行われておらず、日本でもジェンダーバイアスに関して欧米圏と同様の傾向が見られたのか、異なる形で問題が顕在化していたのかは明らかでありません。そこで、内分泌医学、特に性ホルモン研究にまつわる科学史的資料を用いて分析し、日本の文脈に基づいたバイアス是正のためのアプローチを考える足掛かりとします。
「生物学」が差別の正当化に使われない未来に少しでも貢献できるよう、堅実な歴史研究に邁進して参ります。
呉 文慧(神戸大学大学院・研究員)
「特別支援教育で生まれる「サイボーグ的主体」を問う」
この度、私の研究計画が採択されましたことを心より光栄に存じます。まずは日頃から私の研究に協力し応援してくだっている皆さまに、そして選考に携わってくださった方々に、心からの御礼を申し上げます。私の研究は特別支援学校における「人とモノの関係」に注目し、両者の結びつきによって立ち現れる新たな主体としての「サイボーグ的主体」の在り方を探究するものです。こうした探究を通じて従来の「人間中心」の教育理解を超え、教育の可能性、さらには人間の在り方を再考することを目指しております。今回の採択はこの挑戦的な試みの意義を認めていただいた証であり、同時に大きな責任を感じております。今後は研究の深化に努めるとともに、多様な領域の方々との対話を大切にし、成果を社会へ積極的に発信していきたいと考えています。引き続きご指導・ご助力を賜りますようお願い申し上げます。
佐々木 玲菜(ジョンズ・ホプキンス大学・博士課程2年目)
「民意のレッドライン:中国本土における台湾有事への支持の限界を探る実証研究:体制を揺るがす「見えない抑止力」としての世論」
このたびは、ANRI人文学奨学金に採択いただき、心より感謝申し上げます。現在、アメリカで台湾を中心とした東アジア安全保障を研究していますが、現政権下で人文学系研究への資金が縮小するなか、本奨学金は大きな支えとなります。
今回は、中国国内でサーベイを実施し、台湾をめぐる世論と中国共産党の政策決定との相互作用を分析する研究に取り組みます。台湾問題はしばしば米中間の対立として語られ、中国という14億人を擁する社会が「一枚岩」として単純化され、時に悪魔化されがちです。しかし、安全保障は本質的には、人々の恐怖や希望、そして日常生活に根ざした問題です。
本研究を通じて、社会と個人が台湾問題をどのように捉え、最終的な武力衝突の可能性をどう受け止め、何を望み、何を拒むのか——その複雑な構造を少しでも明らかにしてまいります。
高橋 沙也葉(デューク大学大学院美術史・表象文化学科博士後期課程1年/京都大学大学院人間・環境学研究科共生人間学専攻博士後期課程4年)
「芸術と社会の交渉の場としての公共彫刻:芸術/社会的価値、協働、労働モデルをめぐって」
この度はANRI人文奨学金の第一期生に採択いただきありがとうございます。成果発表までに長い時間を要する人文系の大学院生・研究者に投資会社が支援を行うという、貴重な先例となる本取り組みに、奨学生として関わる機会をいただけたことを大変嬉しく思います。私の研究は、「芸術と社会の交渉の場」としての公共彫刻の歴史を対象としています。美術館やギャラリーを飛び出し、人々が社会生活を営む公共空間に設置される彫刻を制作した芸術家たちは、純粋に自らの芸術的関心を追求すればよいというわけではなく、国家・⾃治体・企業による「社会貢献活動の対象としての芸術利⽤」という思惑との交渉のなかで制作を行ってきました。「芸術」と「事業」の接近をめぐる多様な議論を文脈化する本研究を通じて、芸術というものが持ちうる批評的な力や可能性を損なうことなく、存続させ、波及させていくために、今日要請される支援のあり方についても考え続けていきたいと思います。
深谷 拓未(京都大学大学院人間環境学研究科・博士後期課程3年)
「味覚が社会を創る:銘醸地トスカーナを事例とした人類学的研究」
この度は、ANRI人文奨学金に採択頂き、誠にありがとうございます。
私は、大学学部では理工系を専門としていました。しかし、いくら実験と計算を重ねることで、世界の現象に「数値」を与えて理解しようとしても、我々人間の「誤差」や「ゆらぎ」を捉えきることは難しいという壁に突き当たりました。
一方、「味覚が社会を創る」と題する私の研究は、我々が世界や環境を知覚・理解する際の「身体感覚」を問うものです。感覚に左右する要素には、文化や言語・歴史や記憶・物質などが挙げられます。これらの感覚の「誤差」や「ゆらぎ」を、ワイン銘醸地でのフィールドワークを通じて解き明かそうとしています。そして、ワイン生産という農村においては、「味覚」こそ、その社会を特徴付け、形作っているのではないかと考えています。
本奨学金の支援を活かし、感覚と社会との関係を考察し、農村社会の再評価に貢献できれば幸いです。
藤 杏子(立教大学大学院社会学研究科・博士後期課程1年)
「中高年男性の趣味として選ばれるボクシングジムにおける相互作用」
この度はANRI奨学金に採択いただき、大変嬉しく思います。半年前、私は民間企業で働きながら、ダイエットのためにボクシングをしていました。8割以上が中高年の男性というジムの中で出会った人たちは、大変な練習を積極的に行い、楽しげにボクシングをしていました。なぜこのような場が成り立っているのかを考えると、それは人々のふるまいによって成立しているのだと言えます。
私が専門とする社会学のエスノメソドロジーは、まさに、どのようにその場の秩序を成り立たせ、維持しているのかについて、実際の人々の会話やジェスチャーなどに基づいて記述する学問です。このような知見をいかして、趣味の場であるボクシングジム、ひいてはコミュニケーションが促進される場の人々のふるまいについて明らかにしていく予定です。今回のご支援を活かしさらに研究を加速していければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
別當 奏(関西学院大学大学院文学研究科文学言語学専攻・博士後期課程2年)
「安部公房作品における戦後日本の科学受容:1950〜60年代の文学と理工系科学の交差点」
この度は、ANRI人文奨学金に採択いただき、大変光栄に存じます。
私は日本近代文学を専門とし、特に安部公房の文学に焦点を当てながら、1950年代の日本文学と科学・技術との関係を研究しています。戦後の日本では、サイバネティックスや情報科学といった最先端の科学理論が積極的に受容されました。これらは、戦時科学として誕生し、冷戦体制下で発展を遂げたものであり、当時の文学者たちの創造力にも大きな影響を与えました。私は、そうした科学受容の状況と文学表現との関わりを明らかにすることで、文学と科学の学際的なつながりを新たな視点から捉え直す研究を進めています。
今後は、研究をより一層深めるとともに、その成果を教育や社会にも広く還元し、人文学の意義をより多くの人々と共有できるよう努めてまいります。また、この度の奨学金を励みに、分野を超えた研究者の方々との交流を通じて、新たな知の可能性を切り拓いていきたいと考えております。
李 慕遥(大阪大学大学院・博士後期課程三年)
「感染症社会の中の芥川文学」
このたびは、ANRI人文奨学金にご採択いただき、誠に光栄に存じます。私は大阪大学大学院人文学研究科博士後期課程に在籍し、「感染症社会の中の芥川文学」を研究テーマとしております。芥川龍之介の作品には、梅毒やチフス、結核などの感染症が繰り返し登場しますが、それらは単なる医学的・生物学的現象としてではなく、差別や階級構造、ジェンダー、さらには植民地主義や国家権力とも密接に結びついて表象されています。
本研究では、同時代の他作家の作品や新聞メディアの言説とも比較しながら、感染症表象が近代日本社会の秩序や矛盾をどのように映し出しているのかを明らかにしてまいります。
文学と医学、「文系」と「理系」の知を架橋することを通じて、感染症をめぐる社会的理解の深化に寄与し、多様で包摂的な知の構築に貢献できればと願っております。この度のご採択を大きな励みとし、研究に一層取り組むとともに、得られた知見を教育活動や教材開発へ還元してまいりたいと存じます。
渡辺 理子(早稲田大学大学院博士課程)
「主語をめぐる国際関係:地域機構ASEANから主体の在処を問う」
私は大学に拠点を置き、東南アジア諸国連合(ASEAN)を対象として社会科学の見地から検討しています。この研究活動を通して、人文社会分野と呼ばれる領域(以下、「人文分野」)に触れ、貢献しようとしてきました。人文分野の見識は、こうした所属や経歴に関わらずとも、電車の中で見聞きした言葉、気になって調べた事柄、美しいと感じた模様、誰かと折り合えずに終わってしまったやり取り、出かけた先の忘れられない景色などからも生み出すことができるのだと思います。
人文分野の研究は、人が主語になった営みの全てから始まり得るのかもしれません。こうして今回、大学の外の方々とこの研究領域を通して接点ができることは、まだ私(たち)の知らなかった可能性をひらいてくれるかもしれないと期待しています。
※紹介は順不同
審査総評
ANRI人文奨学金プロジェクトリーダー / ANRI シニアプリンシパル
中路隼輔
本年度のANRI人文学奨学金には282件の応募が寄せられ、書類審査を経て28件が二次審査に進んだ。申請内容の水準は非常に高く、一次審査も苦労したが、特に二次審査では、研究の独創性・方法の妥当性・社会的意義のいずれにおいても拮抗し、審査は難航した。最終的に10件を採択としたが、最終候補に残った研究含めて非常に水準が高かった。
ベンチャーキャピタルからの視点としては、web3などの文脈の研究はやはり想定よりは少なかった。また経営学の学問系も、気候変動に関してもやや少なかった気がする。AIは流石に現代のトレンドも重なり多くあった。Pulurarityなどの議論もあるが、やや学問分野というよりはビジネス分野で盛り上がっている議論なのかもしれない。もしくはただそういった方々にリーチができなかったのかもしれないとも思う。特に投資テーマに寄せることは意図はしていないが、投資として盛り上がっているテーマと学問分野との乖離や接続というのは考えていきたいので、そういった意味でも興味深かった。
来年以降も基本的には続けていく予定ではあるので、今回の反省なども活かしながら実行していきたい。そういった意味においても意見などがもしあればANRI中路までXのDMなどでいただければ幸いである。全部にお答えできるかわからないが次回の奨学金含めた活動に生かしていきたい。
※全文の掲載は下記リンクよりご覧ください。
会社概要
会社名:ANRI株式会社
代表者:佐俣アンリ
所在地:東京都港区六本木6丁目10−1 六本木ヒルズ森タワー15F
URL:https://anri.vc/