医療法人社団よしひろウィメンズクリニック
〜受精卵を“命の入口”として見つめる、胚培養士による「対話型医療」の実現へ〜
不妊治療・体外受精を専門とする「よしひろウィメンズクリニック」(https://yoshihiro-womens.clinic 所在地:東京都台東区/院長:佐藤 善啓)は、2025年8月より「培養士外来〜たまごグレード外来〜」をスタートします。
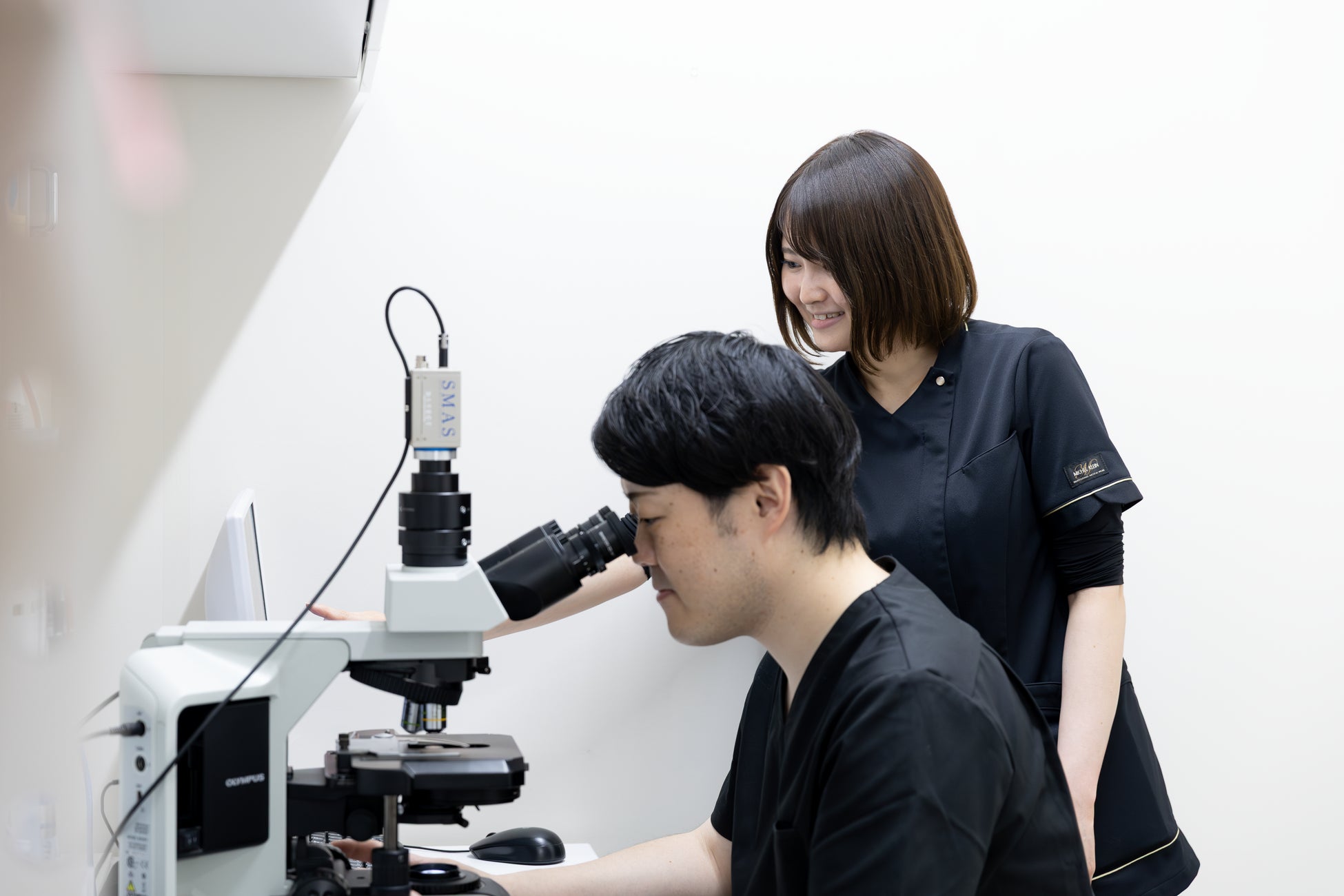
本外来は、構想から約3年の準備期間を経て実現した、全国でも導入例が1割未満(※1)である、胚培養士(エンブリオロジスト)による患者さまとの直接対話を実現した取り組みです。これまで患者さまと直接接する機会が少なかった胚培養士が、採卵後の診療タイミングに合わせて、“見えない存在”であった受精卵の状態を、直接わかりやすくご説明をする「対話型医療」の一つです。
(※1 当院独自調査および関連団体へのヒアリングによる推定値)
体外受精は、身体的、精神的、経済的にも大きな負担を伴い、治療結果が「成功」か「失敗」かの二択で語られてしまいがちな現実があります。実際に、不妊治療を受けている女性の多くが抑うつ症状を経験しているという調査報告もあります。(※2)
だからこそ私たちは、治療のすべての過程が、患者さまにとって“意味のある時間”となるように、一つひとつのプロセスに丁寧に向き合ってきました。
(※2 出典:厚生労働省「不妊治療に関する実態調査報告書(2021年)」)
当院ではこれまで、「夜21時までの診療」「待ち時間の短縮」「土日の診療対応」
「看護師外来〜こころのサポート〜」など、患者さまのライフスタイルや心に寄り添う体制づくりを進めてまいりました。
そしてこの度、さらに一歩踏み込んだ取り組みとして、これまで“見えない存在”であった受精卵との向き合い方に焦点を当てた、新たな外来をスタートいたします。それが、胚培養士が患者さまと直接対話を行う「培養士外来〜たまごグレード外来〜」です。
<「培養士外来〜たまごグレード外来〜」概要>
名称:よしひろウィメンズクリニック「培養士外来〜たまごグレード外来〜」
開始時期:2025年8月
対象:当院にて体外受精・顕微授精を受けられる患者さま
提供タイミング:採卵3日後の来院時(予約不要・診察内での説明)
担当:胚培養士 小野寺、朝田、石津
特徴:
医師による説明に加え、受精卵を最も近くで扱う胚培養士が、受精卵の状態について、患者さまに直接、丁寧に伝える仕組み。
患者さまが治療に対する理解と納得を深め、安心して前に進むための環境づくり。
内容:
・採卵後3日目(受精卵が初期の細胞分裂期にある時点)の来院時に、胚培養士が面談
・受精卵のグレード、成長状況などについての説明
・今後の胚移植に向けた方針や選択肢についての補足
・専門用語を使わず、やさしい言葉での丁寧なコミュニケーション
<現状と課題:不妊治療クリニックにおける「培養士外来」について>
全国の不妊治療クリニックにおいて、「培養士外来」を正式に導入している施設は、全体の1割未満(※3)です。
その理由は、医療法制の壁、人材不足、組織文化の固定観念、説明責任の曖昧さなど、さまざまな要因が複雑に絡み合っていたためです。
“医師が説明し、培養士は語らない”という業界の慣習を超える取り組みとして、院内の調整、体制整備、法律リスクへの配慮を重ね、構想から約3年の歳月をかけてようやく本格的な導入にこぎつけました。
(※3 当院独自調査および関連団体へのヒアリングによる推定値)
<導入背景: “知らされない”ことによる不安や戸惑いを少しでも軽く。「命に寄り添う医療」の提供を目指して>
不妊治療では、「妊娠=成功」「妊娠できなかった=失敗」と、結果のみで評価されがちです。 しかし本来、不妊治療は結果だけで測れるものではありません。
当院は、患者さま側にとって受精卵に対し“感情”が芽生えることが、治療の「成功」、「失敗」という二項対立を超える鍵になると考えます。
受精卵との“感情的な対話”が治療の質を変え、「受精卵=命の入口」ということに丁寧に向き合う時間ができ、患者さまの心に少しずつ変化が生まれていきます。
例えば、「この命と向き合った時間には価値があった」 と認識することにより、単なる「治療」ではなく「命や自分自身と向き合う医療体験」へと昇華させます。
患者さまにとっては、人生観や母性意識の変容を促す大切な時間となり、 私たち医療従事者にとっても、「命に寄り添う医療とは何か」をあらためて問い直す契機となります。
また本来、胚培養士は「バックヤード専門職」と位置づけられ、患者さまと対面する機会が少ない職種とされてきました。
医療法上、診断は原則として医師のみに許される一方、受精卵の状態や治療過程に関する説明は培養士が行っても問題ありません。 しかし、この点が曖昧なまま運用されている施設も多く、「説明=医師の専権事項」という誤解が根強く残っています。
さらに、胚培養士の人材・リソース不足、業務過多(1人で顕微授精・培養・凍結を担うことも多く、外来時間の捻出が難しい) 、さらに医師と培養士の間で情報共有が十分でない点など、培養士の前面への登場が組織文化上難しいという課題感もありました。同時に、患者さま側のニーズも顕在化しにくく、「知りたいけれど聞きにくい」という構造もありました。
しかし、実際には患者さまのなかには、「自分の卵がどうなっているのか」「どんな判断がされたのか」といった情報が不足していることで、“知らされない”ことによる不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。
当院では、こうした患者さまの声に真摯に耳を傾け、医師による説明に加え、「培養士外来〜たまごグレード外来〜」を新たに設置しました。受精卵をもっとも近くで扱う胚培養士が、直接、丁寧にご説明・対話を行うことで、患者さまが治療内容をより深く理解し、納得した上で、安心して次のステップに進める環境づくりを目指しています。
<医療機関としての挑戦:患者さまとの信頼関係と医療倫理の両立>
本来、胚培養士が患者さまに説明を行うことは法的にも認められておりますが、現実には、「何を話してよいか/話してはいけないか」という範囲を正しく理解していない施設も多く、また医師自身が培養士に説明を任せたいと感じていないケースも少なくありません。
こうした現場の理解不足や組織文化的な壁が、全国的に実施率が低い背景となっています。
当院では、「医師の指示の下での実施」「意見表明の範囲の明確化」など、説明内容のルール化と院内合意形成を経て導入に至りました。
<現場の声: “晴れやかに診察室を出て行った”「培養士外来〜たまごグレード外来〜」で深まる患者さまとの信頼関係>
「培養士外来〜たまごグレード外来〜」で患者さまと向き合うのは、受精卵の培養・管理を専門とする胚培養士(エンブリオロジスト)たちです。
これまで診察室ではなかなか聞くことのできなかった「卵のこと」を、もっとわかりやすく、もっと安心して話せるように。本外来の立ち上げに携わった培養士たちが、取り組みに込めた想いや背景について語ります。
【培養士|小野寺 寛典(おのでら ひろのり)】
山形大学農学部卒業後、不妊治療の現場で培った経験を活かし、受精卵の培養・管理を専門とする胚培養士。患者さまが少しでも前向きな気持ちで診察室を後にできるよう、専門用語をかみくだきながら、安心感のある説明と丁寧な対応を心がけている。医療の裏側にある工程を「見える化」し、治療に伴う不安を和らげることを使命としている。日本卵子学会認定 生殖補助医療胚培養士。
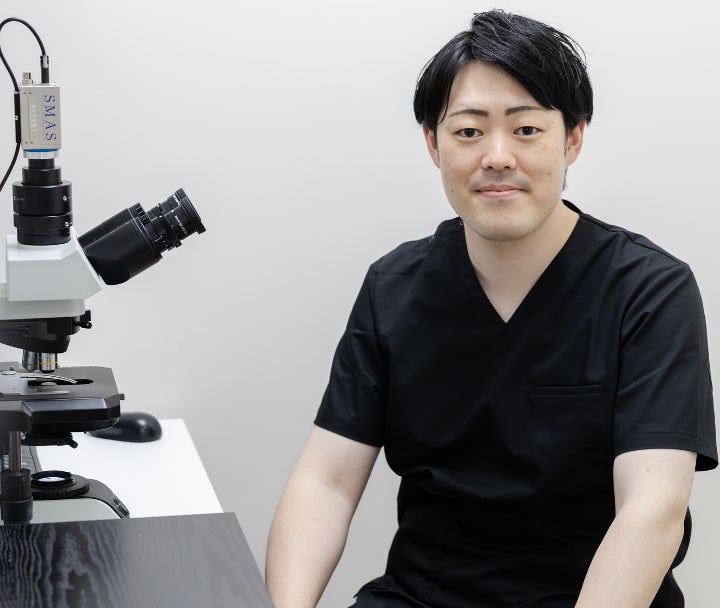
『患者さまが一番気になること「受精卵のグレード」、卵子の質がやはり気になるトピックなのだと思います。この部分を深掘りすることが大切なのだと考えております。
「患者様が治療を進める上で知らなければならないことがとても多い」→「培養士として卵子・精子の質、受精卵のグレードについてわかりやすくお伝えすることが求められている」→「医師の補助として培養士から患者様に直接お話をする機会を設けたい」という思いで培養士外来(たまごグレード外来)を立ち上げました。
先日、診察に同席し、今回培養が上手く行かなかった患者さまに「状況報告」「今回上手く行かなかったところ」「今回上手くいったところ」「上手くいくために今後何が重要か」について15分程度お話をいたしました。先生から「培養が上手く行かなかった患者さまがあんな晴れやかに診察室出て行ったのは始めてです」とおっしゃっていただきました。
もちろん患者様全員の説明が上手く行くわけではありませんが、患者さまの「知らない・わからない」を減らす、辛い治療でも今回「良かったところ」をお伝えすることで少しでも前を向いてクリニックからご帰宅いただくことが重要ではないかと考えております。
医療全般に言えることですが、「患者さまが知っておかなければならないことがとても多い」ということが課題としてあると思います。中でも不妊治療の場合、採血や内診、投薬など、覚えるべきことが多いのに加えて受精や培養状況など、患者さまの理解すべきことの負担は多岐に渡ります。私たちはなるべく専門用語を使わない等、患者さまの理解を深めるお手伝いが必要だと感じています。』
【培養士|朝田 結衣(あさだ ゆい)】
近畿大学農学部卒業後、学生時代にはマウス卵子を用いた研究に従事。前職の兵庫医科大学病院では、一般的な胚培養業務に加え、妊孕性温存のための卵巣凍結や卵子凍結も経験。
父を難病で亡くした経験から、「患者さまやご家族の不安を少しでも軽くし、納得した選択ができるよう支えたい」という思いを胸に、日々患者さまと向き合っている。正確でわかりやすい説明を心がけ、受精卵や卵子の状態を丁寧に伝えることで、治療への理解と安心感を深めることを使命としている。
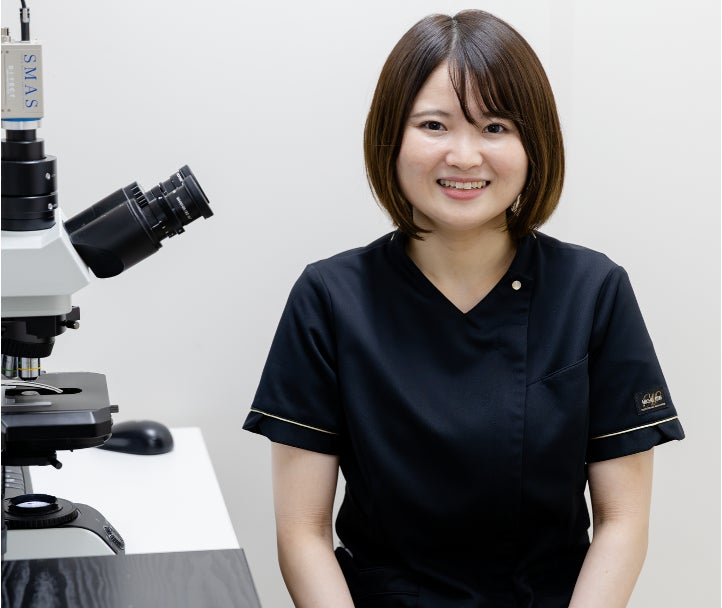
『私は父を難病で亡くしました。
当時は、現実を受け入れることすらできないほど辛く、治療のこともお金のことも、何もかもがわからず戸惑うばかりでした。
そんな中で関わってくださった医療従事者の方々は、多忙な業務の合間にも父に対して本当に丁寧に対応してくださったと思います。心から感謝しています。
それでも、「どうしてこうしたのだろう?」「なぜこうしてくれなかったのだろう?」と、答えのないモヤモヤが残ることもありました。
自分でもネットで情報を調べましたが、正確な情報にたどり着くまでに時間がかかり、ようやく見つけた情報が本当に正しいのかどうか、不安に感じることも多かったです。
「培養士外来〜たまごグレード外来〜」という場を設けることにより、卵子や精子に関する不安を少しでも軽くし、患者さまご自身が納得したうえで人生の選択ができるよう、少しでも力になれたらいいなと思っています。』
<今後の展望>
「培養士外来〜たまごグレード外来〜」は、患者さまがご自身の治療と向き合い、納得して前に進んでいくための「対話型医療」の一つとしてスタートしました。
今後は、より多くの方に安心してご利用いただけるよう、相談体制の拡充や他の外来との連携強化を進めながら、患者さま一人ひとりの不安や戸惑いに、より丁寧に寄り添える「命に寄り添う医療」の提供を目指してまいります。
よしひろウィメンズクリニックはこれからも、「医療の見えにくい部分」を丁寧にひらき、患者さまが“知ること”“納得すること”を通じて、少しでも前向きな気持ちで治療に向き合えるような医療を届けてまいります。
<よしひろウィメンズクリニックについて>

よしひろウィメンズクリニックは、「こころに寄り添う不妊治療」を理念に掲げ、東京都台東区・上野エリアにて体外受精(IVF)を中心とした高度生殖医療を提供する専門クリニックです。
患者様一人ひとりの想いと向き合い、「悩むことも、選ぶことも、あきらめない」ためのサポート体制を整えています。
最新の医療設備と専門医による丁寧な診療に加え、看護師による相談外来や心理的サポート、ピアサポートなど、身体と心の両面から安心して通える環境づくりを大切にしています。
治療の経済的・時間的な効率性にも配慮し、ライフプランを大切にした選択ができるよう、情報提供と対話を重視した診療を実践しています。
公式サイト:https://yoshihiro-womens.clinic/
<本リリースに関する報道関係のお問い合わせ先>
よしひろウィメンズクリニック PR/広報窓口
Mail:yw.clinic.pr@mmany.co.jp